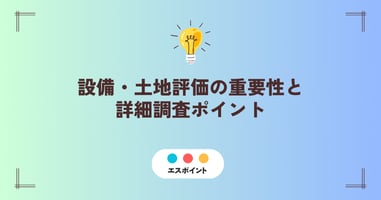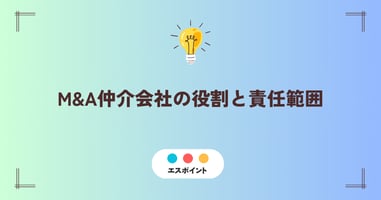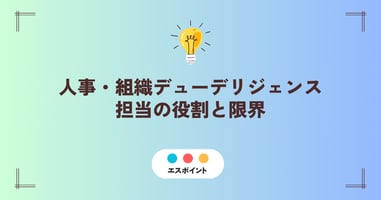Key Points 施設老朽化が 評価額に与える影響 土地鑑定 vs 路線価 2 つの査定方法 更新投資シナリオで NOPAT 差分 を試算 連載ナビ ピラーページ 第1回...
M&Aプロセスでの自己判断ポイントと失敗回避策|第7回 【東北・宮城・仙台】|エスポイント合同会社

Key Points
社会福祉法人のM&Aに初めて臨む経営者・役員・実務担当者の皆さんへ。本シリーズ最終回となるこの記事では、M&Aプロセスにおいて法人自身が判断すべき最重要ポイントを総括し、実践的なチェックリスト(の活用法)をご提案します。
社会福祉法人のM&Aは、その公益性や手続きの複雑さから、専門家の支援が不可欠です。しかし、最終的な意思決定の責任は、常に自法人にあります。 M&Aの成功率は決して高くないという調査結果もありますが、その主な原因の一つは、専門家任せにしてしまい、法人自身の判断軸が曖昧なまま進めてしまうことにあります。しかし、適切な『自己判断』のポイントとプロセスを押さえれば、M&Aの成功確率を格段に高めることが可能です。
本記事では、デューデリジェンス(DD)の結果を受けて法人が自ら判断すべき点を総整理し、専門家任せにしない意思決定の流れ、そして陥りがちな失敗パターンとその回避策を解説します。初めてのM&Aでも、この記事で示すステップと考え方を活用すれば、自信を持って主体的に意思決定を進めることができるようになります。 シリーズの学びを実践に繋げるための『総仕上げ』として、ぜひ最後までお読みください。
【2026年 東北・宮城の市場環境:自前主義からの脱却と戦略的判断】
2026年現在、東北エリアの福祉経営においては、かつての「自法人だけで完結する」モデルから、他法人との連携やM&Aを通じた「地域での生存戦略」へと大きく舵を切る時期に来ています。特に宮城・仙台エリアでは、人口動態の変化を見据えた「不採算拠点の整理」や「成長拠点へのリソース集中」といった経営者の高度な自己判断が、法人の10年後を左右する局面を迎えています。
想定読者:
- 社会福祉法人のM&Aに初めて取り組む経営者・役員・実務担当者
- 専門家(仲介会社・会計士・弁護士等)との関わり方に不安や疑問がある実務担当者
- M&Aの意思決定で何を自法人で判断すべきか明確に把握したい法人の責任者・担当者
ゴール:
- デューデリジェンス(DD)で専門家が提示する報告結果から、法人自身がどのようなポイントを判断しなければならないかを理解する
📑 目次を表示 / 隠す
1.【DD結果の読み解き方】専門家報告から『法人が判断すべき5分野』
M&Aにおけるデューデリジェンス(DD:専門家による調査)では、財務・法務・税務・労務・設備など様々な分野の報告書が提出されます。これら報告書には、買収対象の現状やリスクが専門的観点から分析されています。しかし、報告書の内容をどう評価し最終判断に結びつけるかは、法人自身が担うべき重要な役割です。ここでは、DD報告結果を受けて法人が自己判断すべき主なポイントを、分野別に包括的に整理します。

図1:自己判断すべき5つのチェックポイント
-
財務面のチェックポイント: 過去・現在の財務状況だけでなく、帳簿に表れない負債や将来の収益見通しまで含めて検討します。専門家の財務DDによって貸借対照表や損益の分析が行われますが、法人側では簿外債務(帳簿に載っていない負債)がないか、将来的に事業収益を安定確保できるかまで着目する必要があります。例えば退職給付や訴訟予備費用などの見落とされがちな負債、過大な債務超過リスクがないかを判断します。また、譲渡対価(買収額)の妥当性も財務面の重要ポイントです。社会福祉法人の公的財産を毀損しないよう慎重に検討し、所轄庁から説明を求められても十分説明できるよう判断過程を整理しておくことが求められます。値付けに当たっては、将来の事業計画やシナジー(相乗効果)も勘案し、自法人として「この価格で買っても財政に無理がないか」「投資に見合う効果が得られるか」をしっかり検討しましょう。
-
法務面のチェックポイント: 法律・契約上のリスクや遵守事項について、単なる専門家任せにせず自社で許容範囲を判断します。法務DDでは契約書や許認可、訴訟リスクなどが洗い出されますが、判明した法的リスクに対して最終的に取る対応(許容するか、条件交渉するか、契約に盛り込むか)を決めるのは法人自身です。特に社会福祉法人のM&Aでは、所轄庁の認可や法令遵守が重大な意味を持ちます。平成28年の法改正で定められた「特別の利益供与の禁止」や「利益相反」に抵触しないよう注意が必要であり、事業譲渡の場合は譲受法人が当該事業を実施できる資格を有し継続性が見込まれるかも重要です。また、利用者との契約や雇用契約で引き継ぎが必要なものが確実に移管できるか、不備があればどのように対処するかといった点も検討します。専門家から提示された法的課題について、「自法人として許容できるリスクか」「事前に解消すべきか」の判断基準を持ち、必要に応じて追加の法務相談を行いましょう。
-
設備・資産面のチェックポイント: 買収対象の施設や設備の状態・価値について、長期的視点で評価します。社会福祉法人の施設には老朽化した建物や設備が含まれることも多く、その修繕費用や更新コスト、耐震・防火性能などは財務諸表だけでは把握しづらいポイントです(詳細は第4回参照)。財務DDでは帳簿上の固定資産価値は確認できますが、第4回で解説したように法人自身で現地視察やエンジニアの報告を受けるなどして実物の状態を把握し、将来的な投資額を見積もる判断が必要です。例えば「建替えが何年後に必要か」「設備更新費用を価格交渉に反映すべきか」といった点です。固定資産の実在性確認や外部環境分析により将来リスクを反映することも重要です。DD結果に現れない設備の潜在的課題まで洗い出し、対策を検討しましょう。これにより後から多額の設備投資が発覚するリスクを減らせます。
-
人事・組織面のチェックポイント: 組織文化や人材に関わる点は数字以上に慎重な判断が必要です。人事DDでは就業規則の整備状況や労務トラブルの有無、従業員データなど定量面が報告されます。しかし職場の士気や文化の違い、キーパーソンの去就といった定性的な要素はDDでは掴みきれないため(詳細は第5回参照)、経営陣自ら現場の雰囲気を感じ取り、必要に応じて対象法人の幹部や職員とも面談して判断することが重要です。「組織風土や価値観が自法人と大きく乖離していないか」「買収後に人材流出の恐れはないか」「待遇や役職はどう統合すべきか」など、人に関わる意思決定を行います。特に従業員の処遇統一や役職員の配置については、早めに青写真を描き、双方の職員に不安を与えない判断が求められます。人事面のリスクや課題は数字に見えにくいため、「問題がないように見えるから大丈夫」ではなく、現場の声も踏まえて慎重に評価しましょう。
-
ガバナンス面のチェックポイント: 買収後の組織運営体制やガバナンス(法人統治)のあり方も、法人自身が方向性を決める項目です。DDでは対象法人の評議員・理事・監事の構成や運営状況も情報提供されます。これらを踏まえ、合併後の理事会・評議員会をどう統合するか、あるいは事業譲渡であれば引き継ぐべき運営ルールや内部統制は何かを検討します。例えば、「合併相手の理事を自法人の理事に迎えるか」「買収先のコンプライアンス体制をどう自法人基準に合わせるか」といった判断です。社会福祉法人は非営利法人であり透明性の高い運営が求められるため、統合後もガバナンスが揺らがないよう、意思決定プロセスやルールを事前に整えておくことが大切です。必要に応じて所轄庁への事前相談も行い、監事監査や会計監査の引継ぎについても確認しておきます。こうした組織統治のポイントは専門家が代わりに決めてくれるものではなく、法人の運営方針として自ら意思決定すべき事項です。
以上のように、DD報告で提示された事項ごとに「自法人としてどう判断し、どんな対応をとるか」を整理することが、安心できるM&Aの第一歩です。専門家からの報告内容を鵜呑みにせず自社の視点で咀嚼し、必要に応じてチェックリストを活用しながら一つ一つ社内で検討することが重要となります。
2.【主体的な意思決定プロセス】専門家任せにしないための5つのステップ
M&Aプロセス全体を通じて、法人主体の意思決定姿勢を貫くことが成功のカギです。仲介会社や各種デューデリジェンスの担当専門家は心強いパートナーですが、彼らに任せきりで意思決定を進めてしまうと、後から「こんなはずではなかった」という事態になりかねません。ここでは、専門家任せにせず法人自ら主導権を握るためのプロセスのポイントを解説します。
1.M&Aの目的・戦略を自社で明確化する
専門家に相談を始める前に、まず自法人内でM&Aの目的を明確にしておきましょう。第1回でも述べたように、買収や合併の目的が法人の理念・経営戦略に沿ったものであり、地域福祉の維持・発展に寄与する内容であることが大前提です 。目的があいまいなままでは、専門家から提案された案件に流されて本来望まないM&Aを進めてしまう危険があります。理事会や経営陣で十分に話し合い、「なぜM&Aを行うのか」「どんな条件なら進めるべきか」という意思決定の軸を社内で共有しておきます。これにより、仲介会社から案件を紹介された際も自社の基準で取捨選択しやすくなりますし、デューデリジェンス結果の評価基準もブレにくくなるでしょう。
2.自社で“判断材料”を収集・整理する
専門家から多くの報告や提案が寄せられますが、それらは最終判断のための材料に過ぎません。経営陣および関係部署の担当者が一丸となって、提供された情報を社内視点で分析・整理するプロセスを設けましょう。例えば、財務DD報告について財務担当と経営者が議論し、「懸念点とその影響度」「譲渡価格交渉で考慮すべき事項」を洗い出します。法務DD報告で指摘された契約上の課題については法務担当と現場管理者で「リスク許容範囲か、要是正か」を検討します。このように社内プロジェクトチームや検討会議を通じて、専門家の報告→社内での咀嚼→意思決定という流れを作ります。専門家に丸投げせず「自分たちで理解し評価する」姿勢を組織的に持つことが大切です。
3.重要事項は理事会で慎重に審議する
社会福祉法人におけるM&Aでは、理事会や評議員会といった機関決定が必要となる場面があります。特に合併や重要な事業譲渡は理事会の議決事項ですので、単に専門家の提案を追認するだけでなく、経営陣・理事が十分な説明を受けて判断するプロセスを確保しましょう。例えば仲介会社の選定に関しても、「仲介者を起用すべきか」「手数料は妥当か」を理事会で検討することが厚労省マニュアルでも求められています。仲介会社の提示条件だけで即決せず、必要に応じて複数社の意見や見積もりを比較検討し、理事会で合理性を検証することが推奨されています。これは他の専門家についても同様で、会計士・弁護士などからの報告内容や提案について理事会や幹部会で質問・議論し、自法人としての意思決定を行うことが重要です。専門家の立場では触れられない自社の事情(経営理念や将来ビジョンなど)は理事会が最も理解していますので、そうした観点から最終判断に手を加える役割を果たします。
4.必要に応じ「第三者の意見」も活用する
専門家任せにしないとはいえ、多角的な視点を取り入れる柔軟さも経営判断には欠かせません。特定の専門家の意見に偏りすぎないよう、必要に応じて第三者のセカンドオピニオンを求めるのも一策です。例えば、提示された企業価値評価について自社内で疑問が残る場合、別の会計士に意見を聞くことで判断材料が増えます。また、買収対象の業界動向について業界団体や他法人の知見を参考にすることも有益でしょう。「専門家Aさんがこう言うから従う」ではなく、「専門家Aさんはこう言うが、他の視点ではどうか」を検討することで、判断の妥当性が高まります。もちろん最終判断は自法人で行いますが、複数の専門家や情報源を組み合わせて意思決定の裏付けを強化する姿勢が大切です。
5.意思決定過程を記録し説明責任を果たす
法人主体で意思決定を行うプロセスでは、あわせてその過程を記録に残しておくことも忘れないようにしましょう。誰がどの情報を基に何を判断したかを社内文書や議事録にまとめておくことで、後日「なぜこの決定をしたのか」を振り返ることができますし、所轄庁への報告・説明を求められた際にも迅速に対応できます。特に譲渡価格や重要な契約条件など、公的資産の管理に関わるポイントは、社内決裁書類などで意思決定の理由を明確化しておくと安心です。また、こうした記録は内部統制の強化にもつながり、統合後の監査対応などにも役立ちます。専門家に任せきりでは得られない「自法人としての意思決定の蓄積」を残すことで、今後の事業運営や将来の意思決定に向けた学びにもなっていくでしょう。
以上のプロセスを踏まえれば、専門家のサポートを受けつつも最後は自分たちの判断軸で決めたと言える状態でM&Aを進めることができます。社会福祉法人のM&Aは手続き上も通常の企業M&Aと異なる点が多く、行政機関との調整も必要です。そうした場面でも、自法人で意思決定した事項が明確であれば、ぶれずに対応できるでしょう。
【Tips:Tohoku Executive Choice 2026(東北経営者のための判断基準)】
2026年の宮城・仙台市場では、単なる「規模拡大」ではなく「ドミナント戦略(特定地域への集中)」の是非が問われています。M&Aの判断にあたっては、専門家が示す「収益性」だけでなく、地元自治体(宮城県や仙台市等)の将来的な地域包括ケア計画と、自法人の拠点がどう合致するか、経営者の手元にある「地域密着の勘所」を優先すべき場面が増えています。
図2: M&Aプロセスにおける法人主体の意思決定フロー概念図。
1から5のステップで、目的の明確化から最終決定まで自社で判断すべきポイントを示す。各段階で専門家の助言は参考にしつつも、最終的な意思決定は法人内部で行う流れを表現している。この図の核心は、M&Aプロセス全体を通じて、常に『自法人の目的』に立ち返り、『自法人の責任』で判断を下すという主体性の重要性を示している点です。
3.【失敗回避術】M&A意思決定で陥りがちな4つの落とし穴
どんなに綿密に準備しても、意思決定の過程で陥りがちな「落とし穴」があります。ここでは、社会福祉法人のM&Aにおいて初心者が注意すべき典型的な失敗パターンを事例形式で紹介します。自らの意思決定プロセスを客観視し、同じ轍を踏まないようチェックしてみましょう。
1.目的が不明確なまま進めてしまう
事例: 他法人から「ぜひウチと合併しませんか」と誘われるまま話が進み、気づけば合併の具体交渉に入っていた。しかし合併後に何を実現したいのか社内で共有されておらず、いざ統合しても方向性が定まらない。
解説: M&Aの目的があいまいなまま「とりあえず話を聞いてみよう」と進めるのは非常に危険です。目的不在のM&Aは、交渉過程で意思決定の軸がブレたり、社内の支持を得られなかったりして破綻する可能性が高くなります。上記事例でも、本来合併は手段であり目的ではないのに、誘いに乗って進めるうちに「合併すること自体」が目的化してしまっています。
これを避けるには、第1のステップで目的・戦略を明確化することが肝心です(「専門家任せにしない意思決定プロセス」参照)。「なぜこのM&Aをするのか」を常に自問自答し、目的に立ち返って判断する習慣をつけましょう。目的が明確であれば、交渉過程で迷ったときも立ち戻る指針となり、不要な案件は断る決断力も養われます。これは、セクション2で述べた意思決定プロセス①「M&Aの目的・戦略を自社で明確化する」を徹底することで防ぐことができます。
2.専門家や相手からの情報をうのみにする
事例: 財務DDの報告書で「大きな問題は見当たりません」との結果が出たため、細部を確認せず買収を決定。ところが買収後に未計上の債務や想定外の出費が次々判明し、財務負担が増大してしまった。
解説: 専門家の調査報告や売り手から提供された情報に問題がないからといって、安心しきってはいけません。「売り手は少しでも高く売りたいので都合の悪いことは隠す」というのはM&Aではよくある話であり、提示情報だけで決断するのは極めて危険です。上記事例はまさにその典型で、表面化していなかった負債を見抜けずに高値掴みしてしまったケースと言えます。対策として、情報の真偽や裏側を自ら確認する姿勢が重要です。疑問点があれば追加資料を要求したり、現地で資産や在庫の実査を行ったり、必要に応じて第三者調査機関を使って信用調査することも有効です。「専門家が大丈夫と言ったから…」ではなく、専門家の範囲外も含めて自社でリスクを洗い出す意識を持ちましょう。
また、デューデリジェンス報告書に書かれていない事項(将来の収支予測や経営者個人の資質など)は自社で補完する必要があります(第3回参照)。楽観的すぎるシナリオに基づいて意思決定すると痛手を被る可能性があるため、悲観シナリオでも耐えられるか検討する慎重さも求められます。セクション2のプロセス②「自社で“判断材料”を収集・整理する」段階で、情報の裏付けを取り、多角的に検討することが、この落とし穴を避ける鍵です。
3.人事・組織のソフト面を軽視する
事例: 経営状態の良い法人を買収し順調に合併完了。ところが、合併半年後に旧法人の幹部職員が大量退職し、サービス提供に支障が出てしまった。原因は、合併後の処遇や組織文化の違いに対する不満が蓄積していたことだった。
解説: M&Aでは財務や契約などハード面のチェックに目が行きがちですが、実際の成功可否を左右するのは人や文化といったソフト面であることが少なくありません。上記事例のように、せっかく良い法人を取得しても人材が流出してしまっては元も子もありません。職員の待遇や役割、組織文化の融合計画を事前に十分検討し、丁寧にコミュニケーションすることが必要です。合併・買収による組織再編は当事者(職員)にとって大きな不安を伴うものです。経営陣がその不安に寄り添わず「そのうち慣れるだろう」と放置すると、優秀な人から辞めていくという結果にもなりかねません。
これを避けるため、意思決定段階から人事戦略を練り、必要なら統合作業(PMI)の専門家の助言も得て、ソフトランディングを図る計画を立てておきましょう(第5回参照)。具体的には、給与体系や役職の統一方針、新組織のビジョン共有、キーパーソンとの面談による慰留策などを意思決定時に決めておくと安心です。人事・組織面の統合は数字には見えませんが、M&A成功の要であることを忘れないでください。
4.統合後の計画不足でシナジーを発揮できない
事例: 合併自体はスムーズに成立し、目立ったリスクも表面化しなかった。しかしその後、両法人の業務やシステムの統合作業が進まず、2年経っても組織はバラバラのまま。規模拡大による効率化やサービス向上といった当初期待していた効果は得られていない。
解説: M&Aは契約締結がゴールではなく、その後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)が極めて重要です。意思決定の段階で統合後の具体的な計画を十分に描いていないと、上記事例のようにせっかくの規模効果や相乗効果を活かせません。これも初心者が陥りがちな落とし穴です。「ひとまず買ってから考えよう」では、統合作業が後手に回り混乱する可能性があります。避けるためには、意思決定時に将来事業計画や統合ロードマップを作成しておくことが有効です。
厚労省のガイドラインでも、将来の事業計画策定時には複数年の計画を作り法人の理念や戦略が反映されているか判断するよう求めています。規模が大きくなれば組織も人員も増えますから、経営管理の仕組みを拡充したり、本部機能を強化したりといった対応も必要です。こうした統合後の姿を描かずに意思決定すると、「買ったはいいが持て余す」状態に陥りかねません。意思決定時には、3年後、5年後にどう統合し発展しているかをチームで議論し、ある程度の青写真を持っておきましょう。それが結果的にM&A判断の是非を測る材料にもなります。
| 落とし穴 | 主な症状・状況 | 回避策・チェックポイント |
| 1. 目的が不明確なまま進めてしまう | M&Aの目的が曖昧なまま、相手や仲介会社のペースで話が進み、「合併すること自体」が目的化する。 | なぜM&Aを行うのか、自法人の理念・戦略との整合性は何かを常に問い、目的に立ち返って判断する。 |
| 2. 専門家や相手からの情報をうのみにする | DD報告書や売り手提供情報を過信・鵜呑みにし、リスク(簿外債務等)を見落とす。 | 情報の裏付けを取り、疑問点は徹底的に質問・調査する。悲観シナリオも想定し、多角的に検討する。 |
| 3. 人事・組織のソフト面を軽視する | 財務・法務などハード面を優先し、人事戦略や文化統合を後回しにし、人材流出や組織混乱を招く。 | 意思決定段階から人事戦略・コミュニケーション計画を具体化し、PMIに備える。キーパーソンをケアする。 |
| 4. 統合後の計画不足でシナジーを発揮できない | M&A契約締結をゴールと考え、統合後の具体的なアクションプラン(PMI計画)が不十分。 | 意思決定時に統合後の業務プロセス、システム、組織体制等の具体的な計画・ロードマップまで描く。 |
表: 意思決定時の落とし穴チェックリスト
上記で解説した典型的な失敗パターン(目的不明確、情報鵜呑み、人事軽視、統合計画不足)の4項目について、該当がないか意思決定前に確認するためのリスト例。このチェックリストは、過去の失敗事例から学び、自社の意思決定プロセスに潜むリスクを客観的に点検するための『自己診断ツール』として活用できます。
以上のチェックポイントを押さえておけば、自社の意思決定プロセスを客観的に見直し、危険な兆候に早めに気づくことができます。「自分たちは大丈夫だろう」と過信せず、常にチェックリストを用いて落とし穴にハマっていないか確認する習慣が大切です。
チェックリストの活用方法
- M&A検討の早い段階から定期的に自己診断に活用
- 理事会や意思決定会議で各項目を議題として取り上げる
- 「自分たちは大丈夫」と過信せず、客観的に評価する姿勢を持つ
4.まとめ:自信を持ってM&Aを進めるために
本シリーズ全7回を通じて、社会福祉法人のM&Aにおける役割分担と自己判断の重要性について学んできました。専門家の知見は不可欠ですが、彼らはあくまで伴走者です。最終的にM&Aの舵を取り、その成否の責任を負うのは、経営者・役員・担当者である皆さん自身です。
不安もあるかもしれませんが、本シリーズで解説した視点、特に今回整理した「自己判断すべき項目」「主体的な意思決定プロセス」「陥りがちな落とし穴」を理解し、意識して臨めば、M&Aは決して乗り越えられない壁ではありません。専門家と対等なパートナーシップを築き、自法人の理念と未来を見据えた、納得のいく意思決定を行ってください。
その具体的な第一歩として、実務で役立つ「M&A自己判断ポイント・チェックリスト」をご用意しました。 ぜひダウンロードし、貴法人の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。このチェックリストが、皆さんのM&A検討プロセスにおける確かな道標となるはずです。
専門家の助言と自社の意思決定力を両輪に、自信を持って、より良い未来へ向けたM&Aを成功させましょう! 本シリーズが、その一助となれたなら幸いです。本シリーズの全体像や他の関連テーマについては、ぜひ【社会福祉法人のM&Aにおける役割分担の全体像 記事シリーズ】をご覧ください。
【2026年版 ステークホルダー説明責任チェックリスト】
- □ [所轄庁] 宮城県や仙台市等の所轄庁に対し、M&Aの「公益上の意義」を言葉で説明できるか?
- □ [評議員会] 専門家の報告をベースにしつつも、自法人の理念との整合性を評議員に語れるか?
- □ [利用者] 「サービスの継続性と質の向上」という観点から、納得感のある説明資料が用意できているか?
- □ [地域] 東北エリアでの法人格の持続可能性について、地域住民にポジティブなメッセージを発信できるか?
補足コンテンツ(テンプレート・チェックリスト)
*テンプレートのPDF内にGoogle Spreadsheetのリンクがあります。適宜コピーの上ご活用ください。
参考リンク
- 厚生労働省 社会・援護局「社会福祉法人の合併・事業譲渡等マニュアル」(令和6年改訂版)– 社会福祉法人間の合併や事業譲渡手続きについて解説したマニュアル
- 経済産業省 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」– 中小企業M&Aにおける仲介者の役割や手数料の考え方、トラブル防止策などをまとめた指針(2020年策定、2024年改訂)
- 経済産業省 中小企業庁「中小PMIガイドライン」- 中小企業がM&A成立後の統合作業(PMI:Post Merger Integration)を円滑に進めるための実務的なプロセスや留意点を整理した指針(2022年策定)。M&A後の事業運営や組織融合におけるトラブル防止、シナジー効果創出に向けた取り組みを具体的に解説。
- 厚生労働省医政局委託調査「医療施設の合併・事業譲渡に係る調査研究報告書」(令和2年)– 医療法人や社会福祉法人のM&A事例調査。デューデリジェンスの外部委託状況等についても分析
- エスポイント合同会社「社会福祉法人M&Aの基本と一般企業M&Aとの違い」– 社会福祉法人特有のM&A留意点をまとめた記事。
良くある質問
EBITDA倍率だけでなく DCF+公益性評価 を併用し、複合指標で社内基準を設定します。
重要事項として 2回以上の審議 を行うと所轄庁との協議が円滑です.
契約締結後 30日以内 が目安。遅れると風評リスクが拡大します。