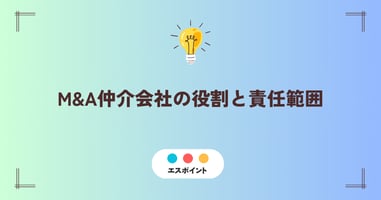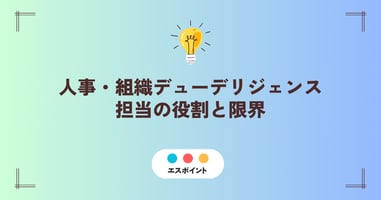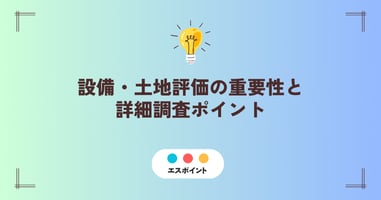Key Points 仲介会社の 4 主要業務 を図解 成功報酬・中間金など 手数料相場 を公開 利益相反を防ぐ チェックリスト 7 項目 連載ナビ ピラーページ 第1回...
社会福祉法人のM&Aにおける役割分担の全体像|第1回|【東北・宮城・仙台】エスポイント合同会社

Key Points
社会福祉法人にとって、M&A(合併や事業譲渡)は、事業承継や経営基盤強化のための有力な選択肢ですが、同時に将来を左右する重大な決断でもあります。特に初めてM&Aに臨む場合、「誰に相談すればいいのか?」「専門家にどこまで任せて大丈夫なのか?」といった不安は尽きません。公益性や行政手続きの複雑さが伴う社会福祉法人のM&Aでは、確かに専門家の支援は不可欠です。しかし、専門家に任せきりにした結果、法人の理念に合わない相手と組んでしまったり、想定外のリスクを引き継いでしまったりして、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも残念ながら存在します。
本記事では、社会福祉法人のM&Aプロセスに登場する主要な専門家(仲介会社、DD担当、FA)の「役割」と「限界」を明確にし、「法人自身が最終的に判断・決断すべき領域」はどこなのかを具体的に解説します。
この記事を読めば、各専門家の「できること」と「できないこと」の境界線が分かり、彼らと健全なパートナーシップを築きながら、法人の未来にとって最善の意思決定を下すための『判断軸』を持つことができます。専門家の力を最大限に活用しつつ、主体的にM&Aを成功に導くための一助となれば幸いです。
【2026年 東北・宮城の市場環境:役割分担の高度化と地域ネットワーク】
2026年現在、東北・宮城エリアでは、社会福祉法人間の連携が単なる「合併」を超え、共同購入や人材シェアリングを含む「多層的な協力体制」へと進化しています。これに伴い、M&Aプロセスにおける役割分担も、単なる契約実務だけでなく、「地域内での新法人の立ち位置をどう調整するか」という、より高度なネットワーキング能力が専門家および法人自身に求められています。
想定読者:
- M&Aを初めて経験する社会福祉法人の理事長、役員、経営幹部
- 社会福祉法人のM&Aに関わる担当者(総務・経営企画担当など)で、プロセス全体像や専門家の役割について体系的な理解を求めている方
- 仲介会社や専門家にどこまで頼れるのか不安を感じ、自法人の責任領域を明確にしたい担当者
ゴール:
- 仲介会社、デューデリジェンス担当専門家(財務・法務等)、ファイナンシャルアドバイザー(FA)それぞれの具体的な役割と支援範囲を明確に理解できる
- 専門家が対応できる業務範囲と、法人自身が判断すべき領域(価格決定や統合後の戦略策定など)を明確に区別し、自法人が主体的かつ責任ある意思決定を行えるようになる
- デューデリジェンス報告書や専門家の助言を正しく読み解き、自法人の経営方針・リスク許容度に基づいて適切な経営判断を行えるようになる
📑 目次を表示 / 隠す
1.【仲介会社】どこまで頼れる?役割と注意点を押さえる
M&Aを進める際、多くの社会福祉法人はM&A仲介会社(アドバイザリー)に相談します。仲介会社は売り手と買い手の橋渡し役として、専門知識を活かしながら取引成立まで様々な支援を行ってくれる心強い存在です。具体的には以下のような基本的役割を担います。
-
マッチング(情報提供): 仲介会社は広いネットワークを活かし、譲渡を希望する法人に対して最適な買い手候補を探し出して提案してくれます。社会福祉法人のM&Aでは、施設の種類や地域ニーズの合致が重要になるため、複数の候補先情報を提供してもらえるのは大きな利点です。また、双方の希望条件を聞き取り、お互いの情報を整理して提供することで、交渉の土台作りを助けます。
-
交渉の仲介・調整: 相手探しの後、具体的な条件交渉の段階でも仲介会社が中立的立場で関与します。日程調整や秘密保持契約の取り交わし支援、初期打診から条件交渉に至るプロセス全般で、クッション役として動いてくれます。経営者同士だけでは言い出しにくい価格や条件面の調整も、仲介者が間に入ることでスムーズになりやすいです。特に社会福祉法人の場合、職員や利用者への影響などセンシティブな論点がありますが、仲介会社は過去の事例知見を持ってアドバイスしてくれるでしょう。
-
契約成立までの支援: 基本合意後から最終契約・クロージングに至るまで、仲介会社はプロジェクトマネージャーのような役割も果たします。必要に応じてデューデリジェンスの調整(後述)や、弁護士・会計士との連携支援、合併認可申請など行政手続きの助言まで行うケースもあります。最終契約書の作成段階でも、法律専門家と法人との間に立ち意見を調整するなど、「成約」に向けたあらゆる段階で伴走します。
しかし、こうした頼れる仲介会社にも限界や注意点があります。まず大前提として、仲介会社は意思決定者ではなく助言者・調整者だという点です。提示された候補先と交渉を進めるかどうか、提示条件を受け入れるか最終判断するのは法人側(経営者や理事会)です。仲介会社は客観的な情報や経験談を提供できますが、最終的にリスクを負うのは貴法人自身となります。
また、仲介会社の立場は「両者の間の中立」とはいえ、収益モデル上は成功報酬(成約手数料)で成り立っています。つまり、基本的には「案件を成立させること」が収入につながる仕組みです。そのため場合によっては、契約成立を急ぐあまりリスクの高い案件でも前に進めようとするインセンティブが働く可能性があります。この点は仲介会社を疑うという意味ではなく、「最終的な責任は自法人にある」という意識を持つことが大切だという意味です。実際、国も仲介会社の手数料や業務範囲については透明性や妥当性を求めており、中小企業庁は中小企業M&Aのガイドラインで「仲介者・FAの手数料体系の明確化」や「重要事項の事前説明の徹底」を取り上げています (「中小M&Aガイドライン」を改訂しました - 経済産業省)。また厚生労働省の作成した社会福祉法人向けマニュアルでも、理事会において仲介者を使う必要性や手数料の妥当性を十分に検討するよう求めています (合併・事業譲渡等マニュアル(改訂版)- 厚生労働省)。例えば、「仲介者の業務内容と手数料金額が客観的に見合っているか判断し、必要に応じて他の業者の見積もりや専門家の意見を参考に交渉すること」まで推奨されています 。
要するに、仲介会社は情報提供と交渉支援のプロですが、「経営判断の代理人」ではありません。例えば、ある法人では、仲介会社が強く推奨する候補先との交渉を進めましたが、提示された高い評価額に疑問を持ちつつも、「プロが言うのだから」と最終的に合意してしまいました。しかし、買収後に想定外の職員離職が相次ぎ、仲介会社が強調していたシナジー効果は得られず、結果的に割高な買い物となってしまったのです。その限界を踏まえ、依存しすぎず主体的に判断する姿勢が求められます。仲介会社から示された企業価値評価や条件提案も鵜呑みにせず、法人のミッションや財務状況に照らして妥当かどうか吟味しましょう。社会福祉法人では公的財産の管理責任がありますから、譲渡対価(M&Aの価格)が適正かどうかは特に慎重な判断が必要です。
【図1: M&Aプロセスの全体像】
上段「売り手側」、下段「買い手側」に分かれ、A・B(準備段階)は各法人が主体となる。C(打診・初期検討)以降の交渉プロセスでは仲介会社等の支援を受けつつ、D(基本合意)、E(デューデリジェンス)、F(最終契約)へと進む。この図は、仲介会社が主導しやすいフェーズ(候補探索や条件調整)と、法人自身が最終判断すべきフェーズ(基本合意内容の是非や価格妥当性)と流れていきます。
仲介会社に任せられる部分と自社で担うべき部分を明確に線引きすることで、専門家を上手に活用しつつ自法人の利益を守ることができます。次章では、デューデリジェンス(買収監査)を担当する専門家の役割と、その限界について見ていきましょう。
【Tips:Tohoku M&A Alignment 2026(パートナー選びの秘訣)】
2026年の東北エリアでは、同じ「社会福祉法人」であっても、地域密着型と広域展開型で経営文化が大きく異なります。仲介会社に候補を依頼する際は、単なる「財務状況」だけでなく、「宮城の地域コミュニティに対する姿勢」や「ICT活用への温度感」が自法人と合致しているか、定性的なマッチングを重視することが成功の近道です。
2.【DD専門家】リスクは見つけてくれるが、「判断」は誰がする?
M&Aにおいてデューデリジェンス(DD)は欠かせないステップです。デューデリジェンスとは、買収対象法人の価値やリスクを適切に評価するための詳細調査のことを指し、財務・法務・税務・人事・不動産・設備など様々な分野のチェックを含みます。社会福祉法人のM&Aであっても、一般企業同様にこの調査は極めて重要です。むしろ、補助金や行政との関係、施設の耐震状況や職員の資格要件など業界特有の項目も加わるため、一層念入りな確認が求められます。
デューデリジェンスは専門家チームによって実施されますが、ここで言う「専門家」とは主に公認会計士・税理士(財務DD担当)や弁護士(法務DD担当)、場合によっては社会保険労務士(労務DD)や不動産鑑定士(不動産DD)など、その分野の有資格者を指します。仲介会社が窓口となってこれら専門家を手配することもありますし、買い手法人が独自に信頼できる専門家に依頼する場合もあります。
デューデリジェンス担当者の主な役割:
-
財務DD(財務監査): 買収対象法人の財務諸表や帳簿を精査し、隠れた負債や過大・過小計上されている項目がないかをチェックします。特に社会福祉法人会計基準特有の科目(例:国庫補助金等特別積立金の処理や退職給付引当金の積み立て状況など)は、専門の会計士でなければ見落としがちなポイントです。財務DDによって不適切な会計処理が発見されれば、将来の修正費用や減損リスクを織り込んで価格交渉に反映させることができます。
-
法務DD(法律面の調査): 弁護士が中心となり、対象法人の契約書や許認可、訴訟リスクの有無を調べます。社会福祉法人の場合、行政からの許認可や指導監査履歴、利用者との契約(利用契約や入居契約)の内容なども確認対象です。特に合併や事業譲渡には所轄庁の認可が必要であり、過去の不備がないか、将来に問題が起きそうな契約条項がないかを洗い出します。法務DDで大きな法的リスク(例えば補助金の不適切受給や重大なコンプライアンス違反)が判明すれば、M&A自体を見直す判断にもつながります。
-
人事・労務DD: 職員の雇用契約や待遇、労働時間管理、資格要件の充足状況など、人事労務面の調査です。これは社会福祉法人特有というより全業種共通ですが、福祉業界では介護職員処遇改善加算の適切な配分や、職員の資格(介護福祉士、保育士など)が必要数確保されているか等、事業継続に直結する項目も確認します。人件費構造や有給休暇残高の引き継ぎコストなども評価し、統合後の運営に支障が出ないかチェックします。
-
施設・設備DD: 社会福祉法人が運営する施設(建物)の耐震状況、設備の老朽度合い、将来的な修繕費用の見積もりなども重要な調査項目です。例えば特別養護老人ホームの建物で耐震補強が必要となれば多額の投資が後から発生し得ますし、老朽化した設備は入所者の安全にも関わります。専門の建築士や設備エンジニアの力を借りて物的資産を評価するケースもあります。
以上のように、デューデリジェンス担当の専門家チームはあらゆる角度からリスクを洗い出し、事前に把握する役割を果たします。彼らの調査結果は最終判断に大きく影響し、報告書に基づき買い手は価格交渉での調整や契約条件(表明保証条項など)の設定を行います。厚労省のマニュアルでも、適正な対価で公的財産が毀損されないよう慎重に検討すべきであり、その過程で弁護士や会計士等の専門家を活用して調査・分析することが有効だとされています (合併・事業譲渡等マニュアル(改訂版))。
しかし、デューデリジェンスにも限界があることを認識しておきましょう。専門家が調べるのは主に過去から現在にかけての事実であり、未来の事業成功を保証してくれるわけではありません。たとえ財務DDで問題が見つからなくても、将来の利用者ニーズの変化までは織り込めませんし、法務DDでOKでも将来的な法改正リスクは残ります。デューデリジェンス報告書は「現時点の健康診断書」のようなものです。健康診断で異常がなくても将来病気になる可能性がゼロにならないのと同じく、DDで問題なしとされた事項も引き続き注意が必要です。
また、デューデリジェンスの結果をどう評価し意思決定するかは最終的に買い手法人の判断です。専門家はリスクを指摘してくれますが、「この案件を進めるべきか辞めるべきか」「提示された買収金額は見合うか」といった統合的判断は下してくれません。報告書に書かれない事項(例えば組織文化の違いや地域からの評判など)もあります。それらは数値化しにくいため専門家の担当範囲外ですが、経営者にとっては非常に重要なポイントです。
現実には、調査項目すべてに専門家を付けると膨大なコストがかかるため、自法人のスタッフが一部のDD役割を担うケースも少なくありません。厚労省の調査研究でも、「デューデリジェンスを含め自法人スタッフがその役割を担っていたケースが多く、包括的に外部委託した例は少ない」と報告されています。特に地方の小規模法人同士の合併では、財務チェックは顧問税理士が行うものの、現場ヒアリングや資産の目視確認は自前で行った、ということもあります。その際に留意すべきは、自社スタッフだけでは専門知識が及ばない分野は無理せず外部専門家に頼ることです。税務など高度な知識が必要な領域は内部対応に限界があると認識し、早めに税理士等に相談したケースもあるといいます。
総じて、デューデリジェンス担当者は「リスクの見える化」を助けてくれる頼もしい存在ですが、リスクをゼロにしてくれる魔法使いではないという点を押さえておきましょう。財務状態や法的リスクの洗い出しはしてもらえるものの、その情報を経営判断にどう活かすかは法人次第です。「このリスクは受容できるか?対応コストを負担してもこの事業を取得すべきか?」といった判断軸をあらかじめ経営陣で共有しておくと、DD結果の解釈を誤らずに済みます。
【図2: 社会福祉法人M&Aにおける役割と責任の分界図】
*クリックして拡大
社会福祉法人のM&Aプロセスと各フェーズの概要。
左側の「M&A戦略」フェーズ(発見~査定)は法人内の意思決定が中心となる領域。
中央の「M&Aの実行」フェーズ(DD~交渉・成約)は専門家(仲介会社・DDチーム)の力を借りながら進める。
右側の「統合とオペレーション」フェーズ(PMI)は再び法人の経営手腕が問われる領域となる。
この図から分かるように、専門家がサポートしてくれる範囲と、最終的に自法人が責任を負う範囲とが段階によって移り変わっていく。
3.【FA】財務のプロの助言、どう活かす?役割と限界を知る
社会福祉法人のM&Aにおいては、仲介会社やデューデリジェンス担当者以外にも、財務・経営戦略面での専門的な助言を提供するファイナンシャルアドバイザー(FA Financial Advisor、財務アドバイザーとも呼ばれます)が重要な役割を果たします。FAは以下のような業務を行います。
-
価値評価(バリュエーション 対象法人の経済的な価値を算定すること): FAは対象法人の財務状況や将来的な収益力を分析し、適正な譲渡価格の算定や妥当性評価を行います。特に社会福祉法人の場合、公的資産や補助金などを適切に評価に組み込む専門性が求められます。
-
財務戦略・資金調達の支援: FAはM&A後の統合に向けて必要な資金調達の方法や、財務戦略の立案をサポートします。統合後の財務基盤が安定するよう、融資条件の交渉支援や返済計画の策定も支援します。
-
財務シミュレーション作成: 買収後の財務状況や経営計画の実現可能性を検討するため、FAは財務シミュレーションを提供します。法人が安心して意思決定を行えるよう、複数のシナリオを用いてリスク評価を行います。
しかし、FAにも以下のような限界や注意点があります。
FAはあくまで専門的な財務アドバイザーであり、最終的な経営判断やリスク許容の意思決定は法人自身が行う必要があります。提供される価値評価や財務戦略案はあくまでも参考であり、鵜呑みにするのではなく、自法人の状況やビジョンに適合しているかを慎重に吟味する必要があります。
また、FAが作成する将来予測やシミュレーションは一定の前提条件に基づくものであり、その条件が変化すれば結果も大きく変わることを認識しておく必要があります。特に社会福祉法人では行政施策の変動や地域の福祉ニーズの変化に敏感である必要があり、これらはFAの提供する情報だけではカバーしきれない分野です。
FAとの連携にあたっては、法人自身が主体的に情報を活用し、最終的な判断責任を持つという姿勢が重要です。FAを適切に活用することで、より精度の高い意思決定と安定した経営統合を実現できるでしょう。
【図3: FAの業務範囲と法人自己責任の整理図】
*クリックして拡大
FAが担う業務範囲の例と、法人自身が最終的に責任を持って判断すべき範囲を視覚的に整理した図。価値評価、財務戦略立案、資金調達支援といったFAの専門領域と、経営判断、リスク受容の判断を行う法人の領域を明確化しています。
4.【法人自身】専門家には任せられない!最終決定すべき4つの領域
ここまで、仲介会社や各種専門家がM&Aプロセスで果たす役割を見てきました。最後に、経営者や法人担当者自身が最終的に自己判断・意思決定すべき領域について整理します。いくら優秀な仲介会社や専門家に恵まれても、これから述べるポイントだけは自らの腹を括って決める必要があります。
-
譲渡価格・条件の最終決定: 価格交渉は仲介会社がサポートしてくれますが、最終的に「いくらで売るか・買うか」を了承するのは理事会など法人自身です。社会福祉法人の場合、財産処分の適正さが問われますので、提示価格が妥当かどうかは経営陣が責任を持って判断しましょう。 厚生労働省の合併・事業譲渡等マニュアルでも触れられているように、公的財産の毀損がないよう説明責任を果たす必要があります。例えば譲渡側であれば簿価や評価額と比較して安すぎないか、買収側であれば将来見込まれる収益に照らして高すぎないか。仲介会社の意見やFAによる価値評価レポートも重要な参考情報ですが、それだけで判断せず、「この価格は、自法人の現在の財務体力で無理なく支払えるか?」「買収によって、具体的にどのようなメリット(シナジー効果)が期待でき、それは金額に見合うものか?」「最悪の場合、どの程度の損失までなら許容できるか?」といった、自法人の視点からの問いかけを通じて、最終的な価格の妥当性を慎重に吟味しましょう。
-
経営ビジョン・統合方針の策定: M&Aはゴールではなく新たなスタートです。特に買収する側(譲受法人)の経営者には、「買収後この事業をどう発展させ地域福祉に貢献していくか」という経営ビジョンが求められます。これはどんな優秀な仲介アドバイザーにも代行できません。合併や事業譲受によってサービス規模が拡大した後、どんな体制で運営し、職員や利用者にどんな価値を提供していくのか、具体的な方針を描くのは経営トップの使命です。PMI(Post Merger Integration、統合プロセス)の専門家に相談することは有益ですが、最終的な方向性は法人自身が決める必要があります。「統合後は現場スタッフ交流の場を設けて文化醸成しよう」「新法人の理事構成は多様性を持たせよう」等、ビジョンや方針は内部から生み出すものです。
-
組織ガバナンスとリスクテイクの判断: M&Aにより組織体制が変わる際のガバナンス設計(理事の追加選任や組織規程の改訂など)も法人の意思決定事項です。仲介会社や弁護士から助言は得られますが、「誰を新法人の要職に据えるか」「合併後の理事長はどちらが務めるか」等は当事者同士の合意に委ねられます。また、デューデリジェンスで判明したリスクについて「どこまで許容し、どこから許容しないか」の線引きも経営判断です。例えば、軽微な法令違反が報告書で見つかったとして、それを是正する覚悟で進めるのか、中止するほど重大と捉えるのか——判断基準は法人ごとに異なります。このリスクテイクの基準を明確にしておくことも大切です。専門家はリスクの存在を教えてくれますが、リスクと利益を天秤にかけて決断できるのは経営者だけです。
-
ステークホルダーへの説明・調整: 社会福祉法人のM&Aでは、所轄庁(行政)への事前相談や認可取得、利用者・家族への説明、職員への説明といったプロセスが不可欠です。これらは経営陣が中心となって行うべき領域です。仲介会社も「説明会開催のサポート」はしてくれるかもしれませんが、実際に説明責任を果たすのは自法人です。特に職員や利用者に対しては、経営トップ自らが今後の方針やメリットを語り、不安を取り除くコミュニケーションが重要となります。地域の関係者や寄附者がいる場合も同様で、自法人の言葉で説明することが信頼確保につながります。
このように、経営者・担当者が自己判断すべき領域は、言い換えれば「専門家に任せられない肝心要の部分」と言えます。M&Aは専門知識が要求されるため外部の力を借りるのは当然ですが、最終的なゴール設定と意思決定だけは外注できません。日本M&Aセンターの解説では「M&Aは外科手術に例えられる」とも言われます。外科手術には執刀医や麻酔医、看護師など多くのプロが関わりますが、手術を受けるかどうかを決断し、自らの生活をどう変えていくかを考えるのは患者本人です。同じように、M&Aという経営上の大手術に臨むにあたって、プロの手を借りつつも自分たちの意思と責任で舵を取る姿勢が求められます。
5.まとめ
社会福祉法人のM&Aにおける役割分担の全体像を、仲介会社・デューデリジェンス担当専門家・ファイナンシャルアドバイザー・法人自身という4つの視点から見渡してきました。仲介会社は案件の出会いから交渉成立まで寄り添ってくれる存在ですが、その助言は中立的であっても最終決定権は持ちません。また、デューデリジェンス担当の専門家はリスクの洗い出しという重要な任務を担いますが、未来の保証はできず、判断までは下しません。そして経営者や実務担当者である皆さん自身こそが、価格や戦略といった核心部分の意思決定者です。
初めてのM&Aでは戸惑う場面も多いでしょう。しかし、本記事で示したように「誰に何を頼るべきか」と「自分たちで決めるべきこと」を予め理解しておけば、各専門家とのコミュニケーションも円滑になります。「ここはプロに任せよう」「ここは自分たちで腹を括ろう」と判断しながら進めることで、無用なミスや後悔を減らし、納得感のあるM&Aを実現できるでしょう。
最後に、本記事のポイントを簡単に振り返ります。
-
仲介会社: 候補紹介や交渉支援のプロ。情報提供と調整役に徹するが、最終判断は下さない。手数料体系やサービス範囲の透明性に留意しつつ、上手に活用することが肝心。
-
デューデリジェンス担当: リスクの見える化を行う専門家チーム。財務・法務など各分野を深掘り調査し、隠れた問題を発見してくれる。ただし未来の事業成功までは保証できず、報告書に書かれない事項も自分たちで考慮する必要あり。
- ファイナンシャルアドバイザー:価値評価・財務シミュレーションの作成・資金調達支援など、専門性の高い財務面での助言を提供。ただし、提供される財務シミュレーションや価値評価はあくまでも一定の前提条件に基づくものであり、法人側はそれを鵜呑みにせず、自法人の状況や将来予測に照らして慎重に検証する必要があり
-
経営者・法人担当者: M&A戦略の立案から価格・条件の最終決定、統合後のビジョン策定まで、最後は自社で決める部分が残る。専門家の意見を踏まえつつも、自法人のミッションや利害に照らした意思決定が求められる。
「専門家に任せる部分」と「自分で決める部分」のメリハリをつけることで、初めてのM&Aでもブレない軸を持って対応できるはずです。社会福祉法人にとってM&Aは利用者や職員、地域社会にも影響のある重大な経営課題ですが、専門家はあくまで信頼できる『伴走者』であり、最終的にハンドルを握り、目的地を決めるのは経営者であるあなた自身です。 信頼できる専門家と二人三脚で進めつつ、自法人の理念と判断を大切にすることで、きっとM&Aという『手段』を通じて、より良い法人運営という『目的』に近づける道筋が開けていくことでしょう。
まずは、今回のM&Aを通じて、あなたの法人が『何を実現したいのか』、その原点となる目的を改めて明確にすることから始めてみませんか? 本記事が皆さまの不安を少しでも和らげ、主体的な一歩を踏み出すための実践的な指針となれば幸いです。
【2026年版 地域M&A推進・ステークホルダー調整チェックリスト】
- □ [行政] 宮城県(または所轄市町村)の担当窓口へ、再編の方向性を内々に相談したか?
- □ [地域] 自治会や地域の民生委員など、再編後に影響を受けるキーマンを特定しているか?
- □ [社内] 専門家チーム(仲介・会計・法務)との連絡窓口となる「法人側プロジェクトリーダー」を任命したか?
- □ [理念] 自法人の理念と、相手法人の「地域に対する想い」に致命的な乖離がないか確認したか?
次回以降の投稿では、仲介会社の具体的なサービス範囲やデューデリジェンス報告書の読み解き方など、さらに踏み込んだトピックを解説していく予定です。本シリーズの全体像や他の関連テーマについては、ぜひ【社会福祉法人のM&Aにおける役割分担の全体像 記事シリーズ】をご覧ください。
参考リンク
- 厚生労働省 社会・援護局「社会福祉法人の合併・事業譲渡等マニュアル」(令和6年改訂版)– 社会福祉法人間の合併や事業譲渡手続きについて解説したマニュアル
- 経済産業省 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」– 中小企業M&Aにおける仲介者の役割や手数料の考え方、トラブル防止策などをまとめた指針(2020年策定、2024年改訂)
- 経済産業省 中小企業庁「中小PMIガイドライン」- 中小企業がM&A成立後の統合作業(PMI:Post Merger Integration)を円滑に進めるための実務的なプロセスや留意点を整理した指針(2022年策定)。M&A後の事業運営や組織融合におけるトラブル防止、シナジー効果創出に向けた取り組みを具体的に解説。
- 厚生労働省医政局委託調査「医療施設の合併・事業譲渡に係る調査研究報告書」(令和2年)– 医療法人や社会福祉法人のM&A事例調査。デューデリジェンスの外部委託状況等についても分析
- エスポイント合同会社「社会福祉法人M&Aの基本と一般企業M&Aとの違い」– 社会福祉法人特有のM&A留意点をまとめた記事。
良くある質問
公益性確保のため所轄庁の認可が必要。スケジュールが +4〜6か月 伸びる点が最大の違いです。
小規模法人なら 仲介会社+会計士 で開始し、案件規模が見えたら FA を追加する方法が費用効率的です。
直近3期の計算書類・施設別利用率・職員構成表・主要契約書(賃貸、リース、融資)が必須です。