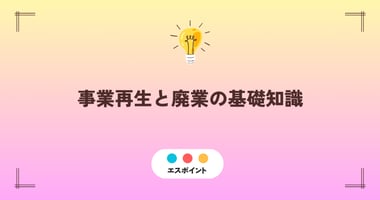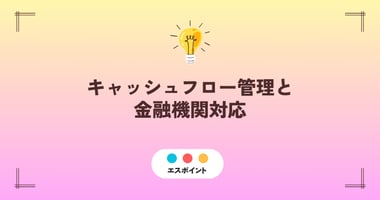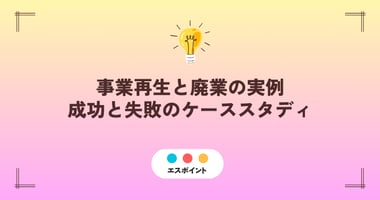経営が行き詰まった企業には、大きく分けて 「事業再生」 と 「廃業」...
第8回:廃業を決断した際の手続きと実務

事業を続けることが困難になり、最終的に廃業を決断することは、経営者にとって非常に難しい選択です。しかし、適切な手続きを踏むことで、経済的・法的なリスクを最小限に抑え、次のステップへと進む準備が整います。本記事では、廃業を計画的に進めるための具体的な手続きや実務について解説し、経営者の新たな道を支援する情報を提供します。
想定読者
- 事業再生が困難となり、廃業を検討している経営者
- 廃業を決断する際の具体的な手続きやリスクを知りたい人
- 廃業後の選択肢を模索している人
この記事のゴール
- 廃業を決断するにあたり、計画的かつ適切に手続きを進める方法を理解し、安心して次のステップへ進めるようになる
- 従業員や取引先への影響を最小限に抑えながら、法的手続きや財務整理を進める実務的なポイントを把握する
- 公的支援制度(中小企業活性化協議会、経営者保証ガイドラインなど)の活用方法を知り、よりスムーズな廃業を実現する
- 廃業後の選択肢(再起業、転職、M&A、事業承継など)を理解し、前向きなキャリアプランを考えることができるようになる
目次
1. 廃業を決める前に再生の可能性を確認する
まずは本当に事業再生(経営改善による存続)の可能性がないか、最終確認しましょう。経営者として廃業を決断する前に、財務状況や事業の見込みを綿密に再点検します。損益計算書や貸借対照表を最新化し、キャッシュフローが将来どう推移するかをシミュレーションします。負債が資産を大きく上回り、営業利益も継続的に赤字であれば再生は難しいかもしれません。しかし一時的な資金繰り悪化であれば、リスケ(借入返済のリスケジュール)や一部事業の売却で立て直せる可能性もあります。専門家の客観的な診断を仰ぐことも大切です。
公的な第三者機関としては各都道府県に「中小企業活性化協議会」(旧・中小企業再生支援協議会)が設置されています。この協議会では、専門家(金融機関OBや弁護士・中小企業診断士等)が企業の状況を分析し、再生の可能性を探ってくれます。もし事業再生が極めて困難と判断された場合でも、「円滑な廃業」や経営者の再スタートに向けたアドバイス、弁護士の紹介などの支援(再チャレンジ支援)を受けることができます (中小企業活性化協議会による支援 | 経営にお悩みの方へ | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構) 。早期に相談すれば選択肢も増えるため、廃業を検討し始めた段階でなるべく早くこうした専門機関や金融機関の担当者に相談しましょう。相談自体は無料で行われ、秘密も厳守されますので安心です。
また、自社だけでは把握しきれていない経営資源がないか見直すことも重要です。例えば不採算部門を縮小・撤退すれば本体事業は黒字化できるとか、在庫処分や遊休資産の売却で資金が捻出できる可能性もあります。取引先や顧客の中に事業継続に協力してくれる先がないか検討するのも有効です(詳細は後述するM&Aによる事業引継ぎの節で触れます)。こうしたあらゆる再建策を試み、それでも難しいと結論した場合に初めて廃業の決断へと進みます。
2. 法的手続きと行政への届出
廃業を決断したら、まず法的な手続きと行政への届出を計画的に進めます。会社組織の場合、廃業するには会社を解散して清算を行う手順が必要です。具体的には株主総会で解散を決議し(株式会社の場合、発行済株式総数の過半数の出席と2/3以上の賛成による特別決議)、代表清算人(通常は代表取締役がそのまま就任)を選任します。その後、法務局で解散登記および清算人就任の登記を行い、会社は清算手続きに入ります。解散後は会社名に「清算中」を付して表記することになります。
解散登記が完了したら、債権者保護手続きとして官報公告や債権者への個別通知を行い、少なくとも2か月の債権申出期間を確保します。並行して財産の清算(後述の「財務整理」の節を参照)を進め、債務の支払い・精算を行います。清算が完了した段階で残余財産があれば株主に分配し、清算結了の株主総会を経て清算結了登記を申請します。これで法人は完全に消滅します。解散から清算結了まで、順調でも数か月〜半年程度は要する点に留意しましょう(債権者への公告期間が2か月必要なため)。
一方、個人事業主の場合は会社のような法人登記手続きは不要です。廃業日を決めたら、その日付で税務署に廃業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出します。税務署への届出は廃業後1ヶ月以内が目安です。合わせて都道府県税事務所や市区町村役場にも事業廃止の届出(事業廃止届、事業所税の廃止届など該当するもの)を提出します。個人事業の場合、法務局への届け出は不要ですが、許認可事業を営んでいた場合には所管官庁へ許可の廃止届を別途提出する必要があります。例えば建設業許可や飲食店営業許可などは、廃業時に許可行政庁へ廃業の届出を行わなければなりません 。
次に、各種行政機関への届け出を漏れなく行います。主な届出先と内容は以下のとおりです:
- 税務署・税務当局:法人の場合、解散日までの期間の確定申告(法人税等)を解散後2か月以内に提出し、清算結了時にも清算事業年度の確定申告を行います。消費税や源泉所得税についても廃業に伴う申告・納税が必要です。個人事業主の場合は、廃業年分の確定申告を翌年3月15日までに行います。さらに法人の場合は税務署と都道府県税、市町村税それぞれに異動届出書(解散・廃止の届出)を提出します。
- 法務局:前述のとおり法人の解散登記・清算結了登記を行います。登記申請の際には株主総会議事録など必要書類を添付し、登録免許税(解散登記1件3万円、清算結了登記は登録免許税不要)を納付します。
- 労働基準監督署:従業員を雇用していた場合、労働基準法関係の手続きを行います。最終の賃金支払いや有給休暇の買取精算などを適切に実施し、従業員に交付する離職票の準備をします(実際の離職票発行手続きはハローワークで行います)。また従業員を解雇(退職)させる場合、少なくとも30日前に予告するか30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります(法定義務)。
- ハローワーク(公共職業安定所):雇用保険適用事業所の廃止届を廃業後10日以内に提出します。同時に従業員の雇用保険被保険者資格喪失届も提出し、失業給付を受けられるよう手続きします。従業員が離職票を必要としている場合も届け出て発行します。
- 年金事務所:社会保険適用事業所(健康保険・厚生年金)の廃止手続きを管轄の年金事務所で行います。健康保険・厚生年金の適用事業所全喪届を提出し、社会保険料の精算をします。従業員の資格喪失手続き(健康保険・年金の喪失)も行い、健康保険証を回収して返納します。
- その他関係機関:業種によって必要な届出があります。例えば飲食店営業なら保健所、建設業なら建設業許可行政庁への廃業届、産業廃棄物収集運搬業なら許可行政への届出など、許認可の返納を行います。また各種団体や組合等に加入していた場合は、その脱退手続きや会費清算も忘れずに実施します。
以上のように、廃業時には複数の官公庁への手続きが発生します。煩雑に感じられる場合は、税理士や司法書士、社会保険労務士など専門家のサポートを受けるとよいでしょう。特に法人の解散・清算登記は司法書士に依頼するケースが多く、税務・社会保険関係は税理士や社労士が代行できます。手続き漏れがあると後日ペナルティや追加徴収を受ける可能性があるため、計画的に進めましょう。
3. 従業員と取引先への対応
廃業を円滑に進めるには、従業員や取引先などステークホルダーへの丁寧な対応が欠かせません。まず従業員については、会社の状況と廃業の方針をできるだけ早めに共有し、公正に扱うことが重要です。
従業員への説明は、正式決定前であっても早期に非公式の場で伝える方が望ましいでしょう。突然解雇通知を受けると従業員は動揺しますし、転職準備の時間も必要です。できれば30日以上前には廃業予定を知らせ、今後のスケジュール(いつまで営業し、いつ付で解雇となるか等)を説明します。併せて解雇予告手当や未消化有給休暇の買取など、法定の補償は必ず実施します。中小企業の場合就業規則で退職金制度を定めていないケースもありますが、長年勤めた従業員がいる場合は可能な範囲で退職金の支給を検討します。退職金は法的義務ではありませんが、従業員の生活の立て直しを支援する意味でも支給が望ましいです。
再就職支援については、公的機関の活用が効果的です。ハローワークと連携し、離職票の発行や失業給付の手続きを速やかに行います。場合によっては地域の産業支援機関や取引先企業の紹介により、従業員の再就職先をあっせんできることもあります。廃業に至った経緯が従業員の責任によるものでないことは明らかですので、「特定受給資格者」として失業保険を受け取れるよう配慮します(会社都合退職となれば待機期間短縮など従業員に有利な給付となります)。従業員にとっても不安が大きい局面ですので、経営者自ら真摯に事情を説明し、感謝の意を伝えることが大切です。
次に取引先への対応です。仕入先や販売先、発注元など主要な取引先には、廃業の事実を早めに伝えましょう。これもできれば営業停止の1〜2ヶ月前には連絡し、書面(廃業のお知らせ)でも正式通知します。取引先にとっては代替先の確保など対応が必要になるため、可能な限り猶予を与える配慮が信頼維持につながります。契約がある場合は契約書に基づき解約手続きを進めます(解約予告期間の順守など)。未納品の注文や進行中のプロジェクトがある場合、それらをどこまで履行するかを決め、履行しない分については正式に契約解除の合意を取ります。前受金や保証金を預かっている場合は返金し、逆に取引先に預けている保証金やリース物件の敷金などは回収手続きをします。
未払い債務の整理も重要なポイントです。取引先への買掛金や未払い費用が残っている場合、廃業までにどこまで支払えるか計画を立てます。資金が不足する場合は債権者(取引先)と個別に相談し、分割払いや一部カットについて理解を求めることも検討します。ただし独断で債務不履行に陥ると訴訟などトラブルに発展しかねません。誠意をもって事情を説明し、可能な限りの支払いを提案することが大切です。取引先によっては在庫品や製造途中の製品を引き取ってくれる場合もありますので、在庫処分について協力を仰ぐこともできます。
借入金の整理と金融機関対応も廃業時の大きな課題です。日本の中小企業では、経営者個人が借入金に対して経営者保証(個人保証)を提供しているケースが多くあります。会社を畳んでも借入金が残れば、保証人である経営者個人に返済義務が及びます。まずは主要な金融機関(銀行や信用金庫)に対し、廃業の意思と今後の返済見通しについて連絡します。金融機関との信頼関係を保つためにも、早めに正直に状況を伝えることが肝心です。返済が困難な場合でも、いきなり返済を止めたりせず、今後の債務整理方針について相談します。
金融機関との調整では、残債務の処理方法として次章で述べる私的整理や法的整理の選択肢を説明し、どの方向で進めるかを協議します。信用保証協会付きの借入金がある場合、保証協会や金融機関は代位弁済や債権回収の方針を持っていますので、それも踏まえて交渉します。例えば経営者保証ガイドラインを活用して保証人である経営者の負担を軽減する手続きを検討したり、法的整理せずに金融機関との個別協議で債務免除を受ける(いわゆる私的整理)可能性を探ったりします。いずれにせよ金融機関側も回収が前提ですので、手元資産でどれだけ返済に充当できるか、親族や支援者からの資金調達可能性はあるか、といった具体策を提示する必要があります。
4. 財務整理と債務処理の進め方
事業を閉じる際には、会社や事業主が抱える債務の整理(清算)をどう進めるかが最大の課題です。資産を売却して負債を完済できれば問題ありませんが、現実には債務超過(負債>資産)で全額返済が困難なケースも多いでしょう。この章では債務整理の具体的な方法と、経営者保証への対応策を説明します。
まず経営者保証の問題です。経営者保証とは、金融機関からの借入に際し経営者個人が連帯保証人となっている状態を指します。廃業して法人が返済できなくなると、保証人である経営者個人がその残債を返済する義務を負います。これを放置すると最終的には経営者個人の自己破産に繋がりかねません。こうした事態を避けるために活用されているのが「経営者保証に関するガイドライン」です。これは中小企業庁・金融庁などの主導で作成された指針で、一定の条件を満たせば経営者個人が破産せずに保証債務(個人保証の借金)を整理できる可能性を示すものです (廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定について(経営者保証に関するガイドライン研究会) | 2023年 | 一般社団法人 全国銀行協会)。具体的には、「誠実な経営を行ってきた」「私財も処分して債権者へ配分する」「廃業手続き開始前に金融機関へ早期相談する」などの条件をクリアし、金融機関の同意を得られれば、残った借入債務について個人保証人の責任を免除してもらえる仕組みです。
経営者保証ガイドラインの適用を受けるには、専門家(弁護士や中小企業再生支援協議会の担当者など)が関与して債権者(金融機関)との協議を進める必要があります。先述の中小企業活性化協議会でも、このガイドラインを用いた保証債務整理の支援を受けることができます (中小企業活性化協議会による支援 | 経営にお悩みの方へ | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構)。ポイントは早期に相談することです。事業継続が困難と分かった時点で速やかに動けば、保証人の残存資産をより多く手元に残せる可能性が高まり(破産に至るより資産流出が少なくて済む)、結果的に債権者への配分も増えて金融機関の同意も得やすくなります。「夜逃げ同然に突然倒産」ではなく、計画的な債務整理に取り組むことが、経営者自身の再起のためにも重要なのです。
次に債務整理の方法について、大きく二つの選択肢があります。一つは私的整理、もう一つは法的整理です。
- 私的整理(任意整理):裁判所を介さず、債権者(主に金融機関や大口取引先)と直接交渉して債務免除や分割返済の合意を取り付ける方法です。メリットは手続きが非公開で進み、社会的信用の毀損を最小限に抑えられる点です (再チャレンジ支援 | 中小企業庁)。また裁判所への費用も不要で柔軟な解決が図れます。ただし全債権者の同意を得る必要があり、一部でも強硬に反対する債権者がいると成立しません。中小企業の場合、主な金融債権者は信用保証協会付き融資を含め数行程度でしょうから、金融機関の理解が得られれば私的整理は有力な選択肢となります。公正を期すため、第三者機関の中小企業活性化協議会や第三者専門家(弁護士・会計士)が仲介する中小企業再生支援ガイドライン(中小版GL)に沿って手続きを進めるケースもあります。これは実質的に金融機関間の調整が図られた私的整理手続きで、債務者企業は破産を回避しつつ債務免除などを受けることができます。
- 法的整理:裁判所に倒産手続きの申立てを行い、法律に基づいて債務を処理する方法です。代表的なのは破産手続きで、裁判所から選任された破産管財人が資産を換価し、債権者に法定の優先順位で配当を行います。残った債務は法律上消滅しますので、企業は清算され、経営者個人も連帯保証債務から解放されます(※経営者個人が保証債務について自己破産し免責許可を得る必要があります)。法的整理のメリットは強制力と最終性にあります。裁判所の手続きなので一部債権者が反対しても手続きを進められ、終了すれば債務問題は完全に清算されます。デメリットは手続きが公開されるため信用情報に破産の記録が残り、取引先にも官報公告等で知られる点です。また裁判所への予納金や専門家費用などコストもかかります。
なお、会社(法人)の場合は特別清算という手続きも法的整理の一種として利用できる場合があります。特別清算は会社法に基づく清算手続きで、主に債務超過ではあるものの債権者の大半と協議済みであるケースで使われます。裁判所の関与はありますが、手続きは非公開で進み、債権者集会で債務免除などの協定が承認されれば残余債務を整理できます。特別清算は債権者の内諾が前提となるため、実質的には私的整理に近い形と言えるでしょう。
債務整理においては、どの方法が最適かはケースバイケースです。負債額や債権者数、財産状況、事業の将来性などによって判断されます。迷った場合は、早めに弁護士など専門家に相談しましょう。中小企業活性化協議会であれば弁護士を紹介してもらえますし (再チャレンジ支援 | 中小企業庁)、日本商工会議所や民間の再生コンサルタントに相談する手もあります。重要なことは、債権者と敵対せず誠実に協議を進めることです。特に金融債務は保証協会経由の場合、保証協会が代位弁済後に経営者個人へ求償してくる流れになります。そうなる前に金融機関ともども保証協会を交えて話し合い、経営者保証ガイドラインの利用や私的整理による解決を図れないか模索しましょう。
資産の整理と換金も債務整理と並行して行います。会社や事業主が持つ不動産、機械設備、車両、在庫、売掛金など換金可能な資産はできるだけ現金化し、債務の弁済原資に充てます。売却に時間がかかる資産については、専門の業者に買取を依頼したり、オークションに出品したりといった工夫が必要です。売掛金の回収も優先度が高いです。取引先に未回収代金をできるだけ早く支払ってもらうよう依頼し、回収資金を債務整理に充当します。こうした資産整理の過程で、会社として残せる資産(例えば従業員への退職金支給分など)と、債権者への配当原資に回す分を分別して管理します。不透明な資産移転や私的流用は厳禁です。債権者との信頼関係を保ち、ガイドライン等を適用してもらうためにも、経営者個人の資産も含め誠実に開示して整理を進める必要があります。
5. 廃業後の経営者の選択肢
廃業は事業の終わりですが、経営者個人にとっては新たなスタートでもあります。ここでは、廃業後に経営者が取り得る代表的な選択肢を紹介します。
(1) M&Aによる事業引継ぎの検討:
廃業を決断する前に、今一度事業の譲渡(M&A)を検討してみましょう。自社としては再建困難でも、他社の資本やノウハウと組み合わせれば事業が存続できるケースがあります。最近では中小企業同士のM&Aも珍しくなく、実際に中小企業庁の統計では年間数千件規模で中小企業のM&Aが成立しています (事業承継を知る - 中小企業庁)。特に後継者不在で廃業せざるを得ない場合など、第三者に会社や事業を譲渡できれば、従業員の雇用や取引先との関係も維持できます。売却益が得られる可能性もありますし、たとえ無償譲渡でも事業が残れば社会的な損失を減らせます。
中小企業のM&A支援として、全国47都道府県に「事業承継・引継ぎ支援センター」が設置されています (事業承継の支援策 | 中小企業庁)。これは国が設置した公的相談窓口で、専門家が無料でM&Aのマッチング支援やアドバイスを行っています。秘密厳守で相談できますので、「会社を売りたいがどこに相談すればよいかわからない」という場合はまず支援センターに問い合わせるとよいでしょう。実際にこのセンターを通じて事業譲渡が成立した例も数多くあります。もちろん民間のM&A仲介会社に依頼する方法もありますが、公的機関をうまく活用すれば費用を抑えつつ客観的な意見ももらえるメリットがあります (まずはこちらへ ~類型と支援機関 - 東京商工会議所)。仮にM&Aが成立しなかった場合でも、事業資産の一部(商品在庫や顧客リストなど)を同業他社に引き取ってもらえるケースもありますので、最後まで諦めずに模索してみてください。
(2) 新たな事業の立ち上げ(再起業):
一度廃業を経験した経営者が再チャレンジして新たな事業を始める例も少なくありません。前事業で得た知見や反省を活かし、より成功可能性の高い分野で再起業するという前向きな選択肢です。日本政策金融公庫などでは、過去に廃業や倒産を経験した人向けの融資制度も用意されています。例えば「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」は、廃業歴のある個人や経営者が新たに創業する際に利用できる融資制度で、最大7,200万円の資金調達が可能です 。ただし利用には条件があり、「前事業の債務整理が新事業に影響しない程度に済んでいること」「廃業の理由がやむを得ない事情であること」等が求められます (再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫)。要するに、不誠実な廃業で多額の未整理債務を残していたりすると新規融資は難しいということです。逆に言えば、廃業時にきちんと債務整理を行っていれば、再スタートのための資金調達の道が開けるということになります。
公的支援としては他にも、中小企業庁の再チャレンジ支援策があります。先述の中小企業活性化協議会による再チャレンジ支援は、廃業後の保証債務整理を支援してくれるものでしたが、加えて新事業への転身支援策として、各種セミナーや専門家派遣、創業支援施策への優遇などが用意されています。また近年では事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジコース)といった補助金も登場しています (事業承継・引き継ぎ等補助金(廃業・再チャレンジ) | 令和3年度 ...) (再チャレンジを見据えて円滑な廃業等を検討している方)。これは、事業譲渡(M&A)が不調に終わりやむなく廃業する場合に、廃業にかかる費用(法人解散登記の費用、在庫処分費、原状回復費用など)や、その後の新規事業に必要な設備撤去費用等の一部を最大150万円まで補助する制度です 。このように、廃業から再出発する際の経済的負担を和らげる措置が拡充されています。経営者にとって再起業へのハードルは決して低くありませんが、周囲の支援策を活用し計画を練ることで、再挑戦も現実的な選択肢となり得ます。
(3) 事業アドバイザーや転職による再出発:
廃業後、すぐに新事業を起こす余力がない場合や、しばらく個人保証の整理に専念したい場合もあるでしょう。そのようなときは、自身の経験を活かせる職場に転職したり、フリーランスの事業アドバイザーとして活動する道もあります。経営者としての経験、とりわけ失敗の経験は貴重な学びです。同業界であれば業界知識や人脈を評価してもらえる可能性がありますし、別業界でもマネジメント経験を買われて管理職として迎えられるケースもあります。また、中小企業を支援する側に回る人もいます。例えば商工会議所や金融機関関連の中小企業支援部署、地方自治体の産業振興機関などでは、実務経験豊富な人材を求めていることがあります。中小企業診断士など資格を取得し、コンサルタントとして活動するのも選択肢の一つです。国の施策でも「第二の人生」として中小企業のメンター役を担うシニア層の活用が推進されています。
廃業の経験は決して無駄にはなりません。事業の失敗から得られる洞察は、教科書にはない実践知です。それを求める企業や起業家は少なからず存在します。「自分は失敗者だ…」と卑下する必要は全くありません。むしろその経験を糧に、次のステージで活躍できる場を探しましょう。過去に事業失敗を乗り越えて別の会社で経営幹部となり成功している例や、コンサルタントとして複数企業の再建に貢献している例もあります。大切なのは前向きな姿勢と、自身の経験を客観的に分析して次に繋げることです。
6. Q&A:よくある質問
Q1. 「廃業」と「倒産」は何が違うのですか?
A. 一般的に「廃業」は事業をやめること全般を指し、「倒産」は支払い不能による経営破綻(法的整理)を指します。廃業には事業承継で閉業する場合や、借金ゼロで自主的に店じまいする場合も含まれます。一方「倒産」は多くの場合法律上の破産手続きを意味し、新聞報道などでも「倒産=破産」のニュアンスです。つまり、廃業=広い意味で事業停止、倒産=債務超過で法的整理と考えるとよいでしょう。ただ中小企業では廃業=倒産(破産)となるケースも多いのが実情です。借金が残っていれば単なる廃業では済まず、結局は倒産手続きが必要になります。
Q2. 会社を清算すれば、残った借金も消えますか?
A. いいえ、会社を通常清算しただけでは借金は消えません。法人を解散・清算しても債務が残れば、債権者は清算人や保証人に請求を続けることが可能です。債務を法的に消滅させるには、裁判所での破産手続きや特別清算手続きを経て免責・免除を得る必要があります。単に事業をやめただけでは債務は帳消しにならない点に注意してください。特に経営者個人が保証人の場合は、会社清算後も個人の責任が残ります。ですから、債務が返済しきれない場合は私的整理で債権者に債務免除をお願いするか、法的整理で整理するかいずれかの対応が必要になります。
Q3. 従業員への退職金や補償は必ず払わないといけませんか?
A. 法律上、退職金の支払いは就業規則や労働契約で定めがない限り義務ではありません。しかし長年働いた従業員に何も支給しないのは現実的に難しいでしょう。せめて功労に報いる意味で可能な範囲の退職金や慰労金を支給するのが望ましいです。また法律上必要なのは解雇予告手当です。30日以上前に解雇予告をしなかった場合、その不足日数分の賃金を支払う義務があります(例:10日前通知なら20日分の手当)。有給休暇が残っている場合は買い上げるか消化させる対応も必要です。資金がなく満額支払えない場合でも、従業員と相談のうえ一部を後日分割で払うなど誠意ある対応を検討しましょう。会社が最終的に破産した場合、未払い賃金については政府の未払賃金立替払制度によって一定額が従業員に支給される救済措置もあります。
Q4. 廃業時の税金が心配です。納めきれない税金があったらどうなりますか?
A. 消費税や源泉所得税、社会保険料などは優先的に支払うべき債務です。これらは未納のまま放置すると延滞税が発生し、経営者に納付義務が移るケースもあります(例えば源泉所得税の滞納は経営者が連帯納付責任を問われる可能性があります)。廃業時にはまず従業員の給与・社会保険と並んで、税金の清算を優先してください。それでも納めきれない場合、税務署に相談すれば分割納税や猶予制度を案内してもらえることがあります。会社が破産すれば法人税や消費税も法的には清算されますが、破産手続き中に税務署が強制執行をかけてくる可能性もあります。最悪の事態として経営者個人が破産しても、租税債務は非免責債権(免責されない債務)とされる場合もあります。いずれにせよ税金は最後まで責任を持って対応する覚悟が必要です。
Q5. 個人保証を外す方法はありますか? やはり自己破産するしかないのでしょうか?
A. 個人保証(経営者保証)を外す手段として、前述した経営者保証ガイドラインの活用が有力です。これに沿って手続きを進めれば、経営者は自己破産しなくても金融機関から保証債務について免除を受けられる可能性があります (廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定について(経営者保証に関するガイドライン研究会) | 2023年 | 一般社団法人 全国銀行協会)。条件としては、経営者が私財提供など誠意ある対応をすること、早めに金融機関と第三者を交えて協議を行うことなどがあります。ガイドラインによる合意が得られなかった場合や保証債務が金融機関以外(親族や知人からの借金など)に多額にある場合は、結果的に自己破産が避けられないケースもあります。ただ自己破産すると今後数年間はクレジットや借入が難しくなるデメリットがあるため、可能であればガイドラインや私的整理で解決を図り、自己破産は最終手段とするのが望ましいでしょう。いずれにせよ専門家に相談し、最善の方法を選択してください。
Q6. 廃業の相談は誰にすれば良いですか?
A. 公的な相談窓口としては中小企業活性化協議会があります。ここでは事業再生や廃業について無料で相談に乗っており、状況分析から具体的なアドバイスまで提供してくれます (再チャレンジ支援 | 中小企業庁)。必要に応じて弁護士など専門家も紹介してもらえます。その他、商工会議所や地域の中小企業支援センター、金融機関の担当者なども相談相手になります。廃業支援に詳しい弁護士や中小企業診断士に個別に依頼する方法もありますが、費用面が心配な場合はまず公的機関を利用すると良いでしょう。いずれにしても早めの相談開始が重要です。手続き直前では選択肢が限られますので、「廃業しようか迷っている」段階で遠慮なく専門家に相談してみてください。
Q7. 廃業後に新しく事業を始めることはできますか?資金調達はできるのでしょうか?
A. はい、適切に廃業処理を行えば再チャレンジは充分可能です。近年は国も「第二創業」「再チャレンジ」を支援する施策を充実させています。日本政策金融公庫の再挑戦支援資金など、前事業の債務整理ができていれば新事業に対する融資を受けられる制度があります (再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫)。また、日本政策金融公庫や地域の信用保証協会は、一定期間経過後であれば過去の失敗だけで融資を拒むことはありません。むしろ事業に失敗した経験を踏まえた計画であれば、初めて起業する人より堅実だと評価される場合もあります。大切なのは、前の事業での失敗要因を分析し、新事業計画に活かすことです。そして廃業時に迷惑をかけた取引先や債権者がいれば、可能な範囲でフォローしておくと良いでしょう。誠実に対応したという信用は、新たな挑戦への支援者や協力者を得る土台になります。
7. まとめ
中小企業経営者にとって、廃業の決断は非常に辛く勇気のいるものです。しかし、事業再生が見込めない場合には、ずるずる延命して被害を拡大するよりも、潔く事業を畳む方が結果的に多くの人を救うこともあります。大切なのは、廃業を思い立ったら計画的に準備し、関係者への配慮と法的手続きをきちんと踏むことです。計画的な廃業を心がければ、トラブルや法的リスクを最小限に抑えることができます。特に債務整理や従業員対応については、事前にシナリオを描いておくことで慌てず対応できるでしょう。
また、廃業は決して後ろ向きな選択肢ではありません。昨今は国も**「事業の再チャレンジ支援」**を掲げ、失敗した企業や経営者の再起を応援しています。例えば中小企業庁の再チャレンジ支援事業では、弁護士による廃業支援や保証債務整理のサポートが提供されており、実際にガイドラインの活用で経営者が破産を回避したケースも増えています 。さらに廃業後の創業支援融資や補助金など、第二創業を後押しする制度も整備されています。こうした公的支援策については以下にいくつか参考となる窓口を紹介します:
- 中小企業活性化協議会(再チャレンジ支援窓口) – 事業再生や廃業の専門相談窓口。債務整理や弁護士紹介、経営者保証ガイドラインの適用支援等 (再チャレンジ支援 | 中小企業庁)。
- 事業承継・引継ぎ支援センター – 後継者不在企業の第三者承継(M&A)を無料サポートする公的機関 (事業承継の支援策 | 中小企業庁)。廃業回避のための事業譲渡先探索など。
- 日本政策金融公庫・信用保証協会 – 再チャレンジ支援融資やセーフティネット保証など、廃業後の資金繰り支援策 (再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫)。
- 商工会議所・中小企業相談所 – 地域の企業支援機関。専門家による経営相談や、廃業マニュアルの提供、専門家紹介など。
廃業に至るまで本当に様々な苦労があったことでしょう。しかし、廃業はゴールではなく新たなスタートラインでもあります。適切な手続きを踏んできれいに事業の幕を下ろせば、きっと次のステップへの道が開けます。本記事の内容が、計画的で前向きな廃業決断の一助となれば幸いです。経営者として最後まで責任を果たしつつ、未来に向けて英断されることを応援します。
次回は、「事業再生と廃業の実例:成功と失敗のケーススタディ」について解説します。実際に再生に成功した企業と、残念ながら失敗に終わった企業の事例を詳しく紹介し、それぞれの要因や学ぶべきポイントを整理します。リアルなケースを通じて、より実践的な事業再生・廃業の判断材料を得るために、ぜひご覧ください。
本シリーズの全体像や他の関連テーマについては、ぜひ【事業再生・廃業ガイド 記事シリーズ】をご覧ください。